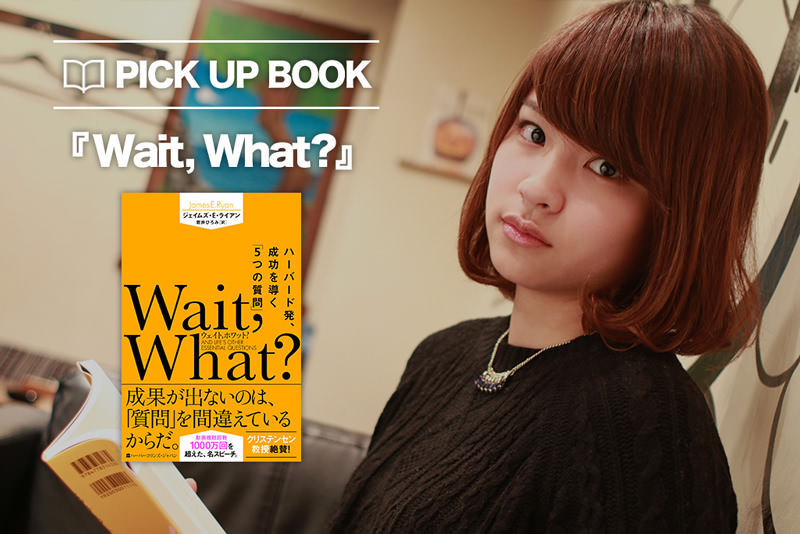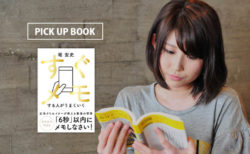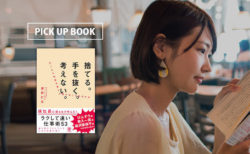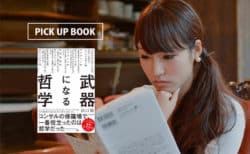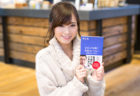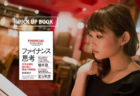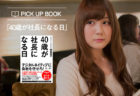こんにちは、社会人一年目の小野寺です。働きはじめて早一ヶ月が経ったわけですが、「気づいたら一ヶ月が終わっていた…」という状態で、一日一日の短さを実感する毎日です。
「目まぐるしい毎日を少しでも充実したものにするにはどうしたらいいのか…?」
そんなことを思い、ハーバード大学教育大学院長が書いた本『Wait, What?(ウェイト、ホワット?) ハーバード発、成功を導く「5つの質問」』を読んでみました。
本書の元ネタは、著者がハーバード大学教育大学院卒業式で行ったスピーチ。「生きていくうえで本当に大切な5つの問い」について語ったこのスピーチは、動画視聴回数1000万回を超えるほど注目を集めました。
「5つの問い」とは次のものです。
- 「Wait,What?」
(待って、何それ?) - 「I Wonder…?」
(どうして、〜なんだろう?) - 「Could’t We at Least…?」
(少なくとも〜はできるんじゃないか?) - 「What Can I Help You?」
(何かできることはある?) - 「What Truly Matters?」
(何が本当に大事?)
以下、人生を変える「5つの問い」についてご紹介していきます。
究極の問いにつながる「5つの問い」
本書で紹介されている「5つの問い」は、著者が考える「究極の問い」に、あなたが「イエス」と答える手助けをするためのものです。
「究極の問い」とは、人生の終わりに誰もが向き合うことになる、非常に重い、次の問い。
「それでもやはり、きみはこの人生で望むものを手に入れたか?」
この問いに「イエス」と答えるために、なぜ「5つの問い」が役立つのでしょうか。著者は次のように説明しています。
- 「待って、何それ?」は、理解の根っこ。
- 「どうして、〜なんだろう?」は、好奇心、探究心の源。
- 「少なくとも〜はできるんじゃないか?」は、前進するための第一歩。
- 「何かできることはある?」は、良い関係を築く足がかりになる。
- 「何が本当に大事?」は、あなた自身の根幹に目を向けさせる。
つまり、「探求と理解を積み重ね、新たな挑戦を厭わず、他者を助け他者から学び、自分にとって大事なものを見失わない」ーーそんな日々を送るためには「5つの問い」が重要であり、それが最終的に「究極の問い」に「イエス」と答えるための手助けとなるのです。
それぞれ詳しく説明していきましょう。
①「Wait,What?」
(待って、何それ?)
「Wait,What?」は、相手の発言内容を明確にし、それを真に理解するために有効な問いです。
わたしたちは、対象が人であれ、アイデアであれ、それをきちんと理解する努力を怠って、早々に賛否を決めてしまいがちです。
たとえば「あの人はこうだから」「これはそういうものだから」というふうに、思い込みや先入観をもとに簡単に結論づけてしまいます。これでは相手に敬意がなく失礼ですし、誤った判断につながりやすいですよね。
早計な判断をする前に、「待って」と一旦スローダウンし、「何それ?」と問う、これによって相手の意見や提案の本来の価値を知るチャンスを得ることができます。
もちろん、理解したうえでなお、判断が変わらない場合もあると思います。それでも、結論を急いだときに比べれば、相手に敬意を抱ける可能性は高くなります。
まず理解して、それから判断する。この習慣が身につけば、無意味な衝突を避けられるのはもちろん、周囲の人々とより深く関われるようになるでしょう。
②「I Wonder…?」
(どうして、〜なんだろう?)
「I Wonder…?」は、好奇心をかきたて、可能性を引き出す質問です。「I Wonder…」のあとに「Why」や「if」を組み合わせて、「どうして〜だろう?」「もしかしたら〜ではないか?」という2つの問いを使い分けます。
これらがセットで紹介されるのは、「どうして〜なんだろう?」と疑問を抱いたら、最後には「もしかしたら〜ではないか?」と問わずにはいられなくなるからです。
「どうして〜だろう?」という問いは、自分の周囲や自分のいる世界に対する好奇心の表れであり、「もしかしたら〜ではないか?」という問いは、未知の世界に一歩を踏み出す原動力となります。
これらは、世界に対して能動的に関わるための重要な問いです。
「どうして〜なんだろう?」と問い続ける限り、周囲への興味を失うことはありませんし、「もしかしたら、〜できるのではないか?」という問いによって、周囲に能動的に関われるようになるからです。
好奇心を失わずに生きることの重要性は、堀江貴文さんの著書『多動力』でも説かれているので、ぜひ参考にしてみてください!
③「Could’t We at Least…?」
(少なくとも〜はできるんじゃないか?)
この質問は、状況を打開し、前進させる質問です。
仕事でもプライベートでも、人と意見がぶつかってしまい、合意がとれないことってありますよね。そんな時、「少なくとも、〜はできるんじゃないか?」と問うことで、お互いが立ち止まり、譲歩や妥協の余地はないかと考えることができます。
お互いがいがみ合ったままでは、前進しないどころか、関係が悪化する可能性が高いですが、この問いによって互いに歩み寄ることができれば、建設的な関係を築くことができます。
また、「少なくとも〜はできるんじゃないか?」という問いは、自分が挑戦を迷っている際にも、前へ進むための原動力になってくれます。
「合意がとれない」、「勇気がでない」、「失敗するかもしれない」。そんな気持ちが頭をよぎった際は、「少なくとも〜はできるんじゃないか?」と自分に問いかけてみましょう。
ベストではなくベターを志向することで行動のハードルを下げ、試さないことによる後悔の可能性をなくしてくれる質問なのです。
④「What Can I Help You?」
(何かできることはある?)
この質問は、相手の力になろうとする意志と、相手への敬意を示すことができ、良好な人間関係を築くのに役立ちます。
他人を助けることは、素晴らしいことです。しかし「あの人にはこれが必要でしょ」と自己中心的に決めつけたり、「助けるのは自分しかいない」と思い込んで、救世主のように振舞ったりしては、逆に迷惑がられてしまう可能性もあります。
「何かできることはある?」と問えば、「あなたのことをいちばんわかっているのはあなたです、だからたとえわたしが手を貸したとしても、仕切るのはあなたです」という気持ちを相手に伝えることができます。
また「私はあなたを助けようとしているけれども、あなたがわたしを助けてくれる可能性もあるんですよ」と、言外に伝えることができるため、相手とより対等な関係にしてくれる問いでもあります。
⑤「What Truly Matters?」
(何が本当に大事?)
最後の問いは、あなた自身の考えや目標を明確にしてくれる質問です。人生のあらゆる場面で、大事な事柄とそうではない事柄を選別し、些末なことに時間を使ってしまうことを避けることができます。
人は往々にして、何が大事かを見失ってしまいます。その理由について著者は、「行動がパターン化してしまい優先順位に注意が向かない」「自信のなさから、眼前の難題ではなく枝葉の問題に取り組んでしまう」ことなどを挙げています。
絶えず「何が本当に大事?」と問うことで、あなたの人生における優先順位が明確になり、難題と向き合う勇気が湧いてきます。
大事なことがわかったら、その答えに沿った人生を送るための具体策を、この問いを繰り返すことで見つけましょう。
「何が本当に大事?」と問うときに重要なポイントとして、著者は次のように指摘します。
あなたにとっていちばん大事なものは、あなたにしかわからない。(中略)人に対しても自分に対してもだが、より重要なのは、自分自身に問いかけることだ。そして、正直に、恐れずに、答えること。そうすれば、ものごとの要点や本質が見えやすくなる。あなたの人生の核心も、また。(p.134)
私自身、周りの目や自分の立場などを気にしすぎず、「何が本当に大事?」と自分に問いかけ、自分の言葉で正直に答えていきたいなと思いました。
5つの問いで、人生を豊かにしよう!
本書は、人生に対して答えを提示してくれる本ではなありません。ただ、この本は、「自分の人生」の考え方を提示してくれる本です。
とくに5つ目の問いは、私自身に「人生の中での大事なもの」を改めて考えさせてくれる問いとなりました。本当に大事なものがわかれば、仕事もそうですが、毎日の生活における物事の優先順位も変わってきます。社会人になりたての今のタイミングで、この本に出会えて幸いです。
習慣的に5つの問いを利用し、行動する。そして自分の人生を通して「本当に自分が望むものを手に入れたぞ!」といえる自分でありたいなと思います。
読者の皆様も、究極の問いに「イエス」といえるよう、5つの問いを利用してみてはいかがでしょうか。