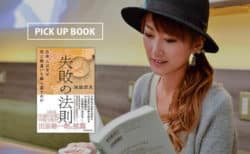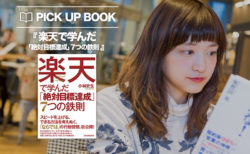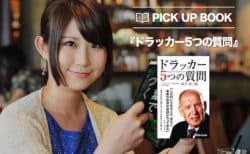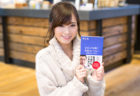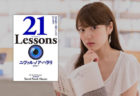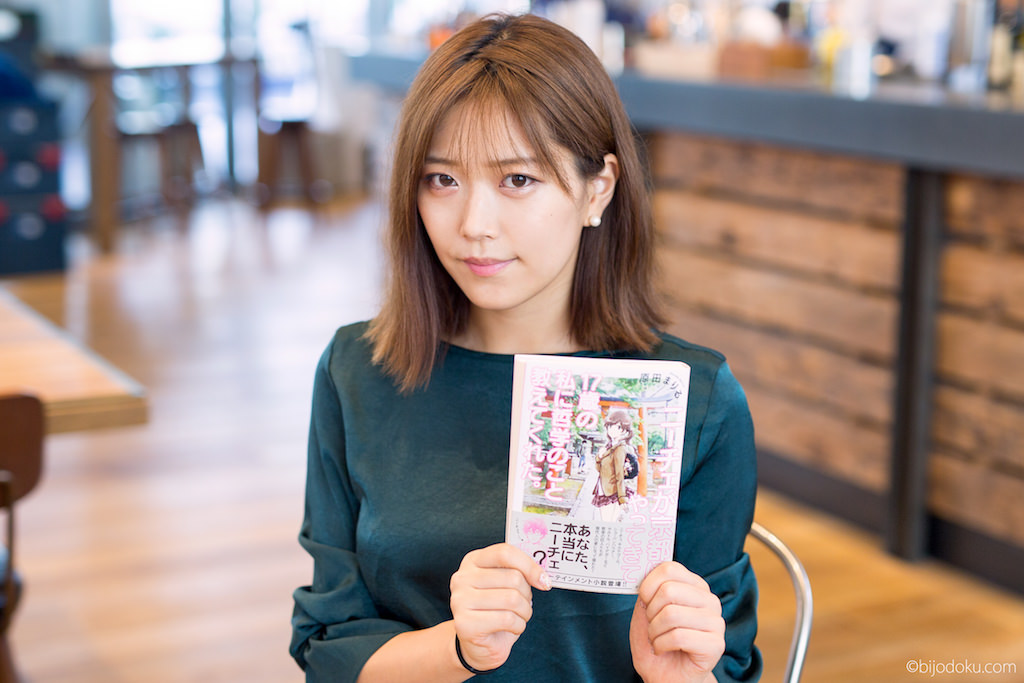こんにちは、ひとはです。
ビジネスの世界に関心のある人であれば、トヨタの生産方式について耳にしたことがあると思います。「かんばん方式」や「アンドン」「カイゼン」といった独自のネーミングがなされていることでも有名ですが、それが今や世界の標準となっていて、「KAIZEN」という言葉は英語の辞書にも載っています。
本書は、「トヨタの習慣」をテーマに書かれた本ですから、生産工場における効率化に関する内容と思われる方もいるかもしれません。しかし読んでみると、トヨタで行われていることは、私たちの日常にも役立つことが多く含まれていることがわかります。
オフィスワークの方も、自営業の方も、学生の方も、トヨタの習慣の中から自分の仕事やミッションの生産性を高め、アウトプットの質を向上させるヒントを得ることができるでしょう。
著者の「OJTソリューションズ」とは、トヨタに40年以上勤務された方々が、その経験を元に人材育成や変化に強い現場づくり、あるいは儲かる会社づくりなどの面でトヨタ以外の企業への支援を行っているコンサルティング会社。
本書は、トヨタで実際にトレーナーとして指導されていた方々が、トヨタで習慣として行われていることを、分かりやすく実例を挙げて紹介していますので、誰にでも理解しやすい内容になっています。
その中でも多くの人に役立つ内容をご紹介しようと思います。
ラクをすることが改善につながる
トヨタ生産方式を支えているのが「改善」です。徹底的にムダを省き、生産効率を上げるために、今よりも更に良いやり方に変えていく活動ですが、「改善」とは、言い換えれば、現場の「困った」を解決することでもあります。
作業がやりにくいとか、会議が多いとか、勉強が追いつかないとか、読者の方もそれぞれの立場で様々な困りごとがあるのではないでしょうか。そのようなときに、どうしたらラクになるのだろうかという視点を持つことが重要だと言います。
その発想によって、今までにない切り口で新しいやり方を考えることができるようになり、改善が進むからです。
ラクになる方法を考えることで改善ができて、結果として生産性が上がることになるのですから、トヨタの発想は、人を大切にすることが根本にあると感じます。
人を責めるな、しくみを責めろ
トヨタ生産方式で有名な言葉に「アンドン」というのがあります。これは、生産ラインにおいて、何か異常が発生したら、作業スペースに張られている紐を引いて、ラインを止めるしくみのことです。
クルマの生産ラインを止めてしまうのですから、少々のことではなかなか紐を引く勇気が出せないのではないかと思ってしまいますが、トヨタの考え方は逆です。つまり、問題が小さなうちに潰しておくことで、のちのち大きな問題を引き起こさないようにするという考え方なのです。
更に、問題が起きたところで作業を止めてしまえば、問題が起きた時の状況がそのまま保存されていますので、再発防止策を見つけやすいというメリットもあります。
このように異常が発生したらすぐに報告するということは、悪い報告こそすぐに上司に報告するということであり、「バッドニュース・ファースト」という習慣ができているということなのです。
それは問題を起こした人を責めるのではなく、問題を起こしてしまうようなしくみが悪いという考え方が浸透しているからです。こうした環境の下では、上司や周囲が「問題を見つけてくれてありがとう」という気持ちで受け止めてくれるのです。
当たり前のことをやりきる凡事徹底
凡事徹底とは、聴き慣れない言葉ですが、「誰でも出来ることを、誰にも出来ないレベルまでやること」と解説されています。
当たり前のことを確実に行っていれば、その仕事を極めることもできるでしょうし、いつもと違う小さな変化があったときには、いち早く問題を見つけることができるのです。そのような事例をひとつ紹介しましょう。
トヨタの工場は掃除も徹底されているので、敷地内にはゴミはほとんど落ちていないそうです。ある日、従業員の一人が、敷地内の道路にナットが一つ落ちているのを見つけます。不思議に思って見ていると、別の従業員が「けん引台車の部品かもしれない」と指摘しました。そこで、工場内のすべてのけん引台車を点検すると、ナットが外れているものが見つかったそうです。そのまま気付かずに放置しておけば、タイヤが外れて大きな事故になっていたかもしれません。
凡事徹底していると、落ちているナットひとつからここまで気付づきを得て、問題を未然に防ぐことができるのです。
やってみせ、やらせるだけでは不十分
仕事を誰かに教える場合には、まず自分でやって見せてから、やらせてみるということが一般的でしょう。あるいはマニュアルや作業標準書といった文書で仕事の内容を伝えることもあるでしょう。
これに対してトヨタでは、「やってみせ、やらせてみせて、フォローする」ことが基本です。この「フォローする」という部分が大切で、作業の勘どころや急所と言われる重要な部分について、なぜそうするのかを説明するのですが、それだけでなく、作業をやらせてみてから急所となる部分やその理由がどのようなことであるのかを口に出して言わせてみるのだそうです。
それは単純な作業であっても、それがどのような意味を持つものであるのかを理解するまでフォローするということであって、一人ひとりの能力が向上し、生産性が上がり、付加価値の高い仕事を生むことができる秘訣なのです。
トヨタの常識は、世間の非常識
トヨタで長年働いていた方が、他社の改善指導に取り組むと、トヨタで当たり前に行われていたことが、指導先の会社ではできていないことがあるそうです。
そのような例から考えると、この「トヨタの常識は、世間の非常識」という言葉は、世界一のトヨタが自社の仕事の習慣を自慢しているように聞こえるかもしれません。しかしそれはまるで逆で、トヨタで当たり前にやっていることが、本当に最善のやり方なのか戒める言葉なのです。
別の言い方をすれば、井の中の蛙のような状態になっていないか、ということを常に自らに問いかけているということなのです。
世界一と言われる企業になっても、驕ることなく、こうした謙虚な考え方が「習慣」として浸透している会社であるからこそ、グローバルに戦い続けることができる強い企業体質を育んでいるのでしょう。
まとめ
本書の中から幾つかの「トヨタの習慣」をご紹介しました。世界で一、二を争う自動車メーカーでありながら、いずれも現場に密着した小さなことを地道にやっている印象を持ちました。
それらは、木目細やかな心配りができる日本人だから出きる内容と思えるものもありますが、冒頭でも書いたとおり、トヨタの生産方式は日本のものづくりの真髄を表すものとして全世界に広まっています。
それはトヨタのやり方がどのような国の、どのような人にも受け入れられているということであり、世界中で通用する普遍的な内容であると言えるでしょう。
自動車の世界は今、大きな変革期を迎えていると言われています。ガソリンエンジンのクルマから電気自動車などの環境に優しい車への転換が進んでいますので、トヨタといえども世界中の自動車メーカーと激しい競争をしていることでしょう。
販売競争だけでなく、技術開発競争も熾烈でしょうが、その戦いを支える企業の底力というものが、この「トヨタの習慣」なのではないかと思います。
それはトヨタが、長い歴史の中で習慣となるほどに愚直にやり続け、成果を出してきたことなのです。