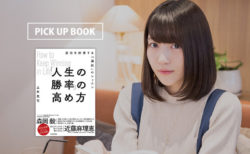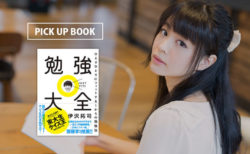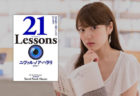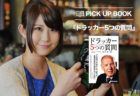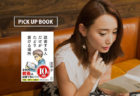2018年に出版された落合陽一さんの著書『日本再興戦略』。
落合さんの革新的な考え方に触れた私は、今年出版された新刊『日本進化論』にはどんなことが書かれているのだろうと興味を持ち、手に取ってみました。
本書は、2018年7月に落合陽一さんと小泉進次郎さんの共同企画で開催されたニコニコ動画の生放送番組「平成最後の夏期講習」と、そこで展開された議論をもとに書かれています。
本書のキーワードとなっている「ポリテック」という言葉。これは「ポリティクス(政治)」と「テクノロジー(科学技術)」を掛け合わせたものです。
戦後につくられた社会制度の多くが、耐用年数を過ぎて時代に合わなくなっていて、さまざまな局面で政治(ポリティクス)が機能不全を起こしています。
そこで技術(テクノロジー)による問題解決を選択肢の一つとして持っておくことは、日本の未来のために望ましいことだと落合氏は述べています。
本書では「働き方」「超高齢社会」「子育て」「教育」「社会保障」「スポーツ」という6つのテーマについて、それぞれが抱える問題と、ポリテックを活用した解決策が書かれています。
ここでは「超高齢社会」に絞り、落合氏の解決策を紹介します。
テクノロジーで超高齢社会を解決する
2018年9月総務省の発表によると、日本は高齢者が全人口の28%以上を占める「超高齢社会」だそうです。
さらに、2060年には全人口の約40%が高齢者で構成されるようになるといわれています。
高齢者の割合が増えることによって生じる問題と解決策は様々ですが、本書では、最近ニュースで取り上げられることの多い「高齢者ドライバー問題」が具体例として検討されています。
高齢者の事故だけが減らない理由
なぜ最近になって高齢者の自動車事故が問題になっているのか、疑問に感じている人もいるのではないでしょうか。
日本での自動車の大衆化が本格的に始まったのは、1964年の東京オリンピック以降です。この時期に20歳前後だった人々が、現在、後期高齢者に突入しはじめています。
つまり現在の高齢者は、日常的に自動車に乗るようになった一般層の最初の世代というわけです。
半世紀近くにわたる運転歴があるため、自動車のある生活が当たり前になっており、運転技術にまだまだ自信があるという人もいるでしょう。
何より、交通インフラが発達している地域の方が運転免許の返納率が高い、というデータが示している通り、地方在住で自動車がないと生活できない環境のため、やむなく自動車を運転し続けているという人も多いはずです。
この問題に対して、3つのアプローチによって解決していくべきだと落合氏は述べています。
高齢者の自動車事故を防ぐ3つの方法
①ドライバー監視技術
高齢者が自動車事故を起こす直接的な要因は、高齢者の身体的・認知的能力の低下にあるようです。
そのためドライバーの状態を常にチェックするという方法が有効な解決策になるはずだと言われています。
たとえば、ドライバーの顔を常時カメラで撮影し、画像解析によりドライバーの不注意やわき見、居眠りなどを検知することで注意喚起するという技術があります。
将来的には、ドライバーの判断力や認知能力が基準を下回ったという判断をAIが下した場合、警告が出たり、危険な場合にはエンジンを強制停止するといった機能も実現されるかもしれません。
②自動運転技術
運転中の危険を察知して警告を発したり、自動ブレーキがかかったりする機能が搭載されることで、事故率は大きく低下するでしょう。
現在、自動運転は「レベル3」(条件付き運転自動化)にあり、限定された条件のもとでなら、すべての運転タスクが自動化される段階にあるといいます。
内閣府は2020年を目処に自動運転レベル3の市場化を目指すとしているそうです。高速道路や大きな幹線道路で運転可能となる日は遠くないようです。
③コンパクトシティ化
3つめの解決策は、人々が暮らす都市そのものを、自動車が要らない形に変えるというアプローチです。
ショッピングモールや病院といった、生活に必要な施設の近くに住宅地を配置して、徒歩やバスで通えるようにすれば、自動車に頼った生活から抜け出すことができます。
生活圏が広範囲に及ぶ社会は、インフラ維持にコストがかかります。
これからの人口減少社会では、都市を縮小し生活圏を限定することにより、様々な問題を同時に解決できるようになると言います。
「お世話介護」から「自立支援」へ
本書では、各章の終わりに「議論のまとめ」と「コラム」が掲載されており、各分野の第一人者の方が筆をとっています。
「超高齢社会」の章では、株式会社メディヴァ代表取締役社長・大石佳能子氏が「介護」について触れています。
大石氏によると、日本は2025年までに、あと55万人の介護人材を増やす必要があるそうです。これは、現状の約30%の人数にのぼります。
介護問題における人材不足を解決するには、テクノロジーの活用が必須です。たとえば、夜間の見回りは約15人を1人で見守る体制になっていますが、センサーで夜間の見回りをすることによって、50人の高齢者を1人で見守ることができるようになるといいます。
また、薬で治療できる病気から、認知症や糖尿病のような生活習慣病へと病気の中心が変わってきたことにより、治療だけでなく、予防・ケアを含む対応が必要となりつつあるようです。
病気になってから治すのではなく、予防・悪化防止に力を入れ、むやみに入院させるのではなく、自宅や高齢者住宅で自分らしく過ごしてもらう。人手に頼った介護ではなく、テクノロジーを活用する。
これまでの「お世話介護」から「自立支援」へと社会全体の価値観の変化が求められているようです。
ポリテックは名前をつけてからがスタート
冒頭で紹介したキーワード「ポリテック」。落合氏は、この言葉を使うところからスタートするべきだと思う、といいます。
最初のうちは意味がはっきりしないままツイッターなどでつぶやかれるだけかもしれないけれど、そのうち人々の間で共通の観念が育まれ、そこから議論がはじまるのを期待したいというのです。
本書を読んで「ポリテック」について考えてみるのはいかがでしょうか。