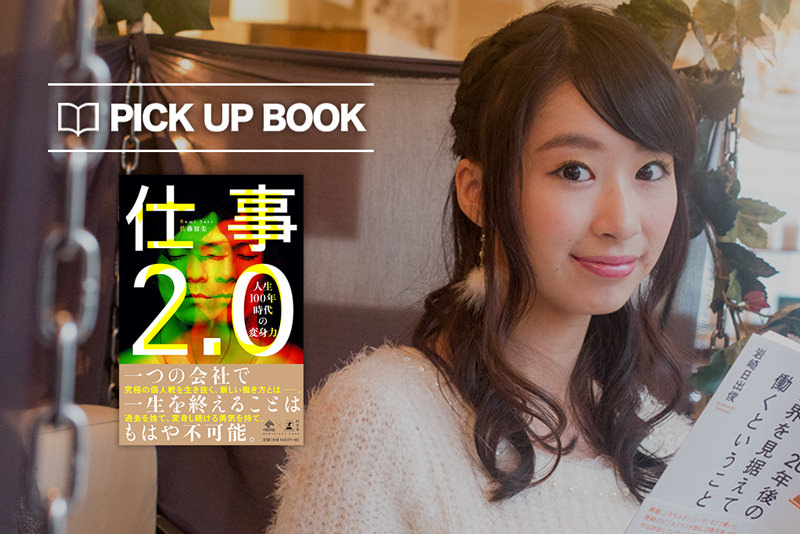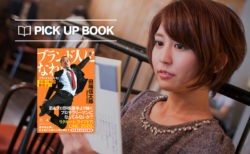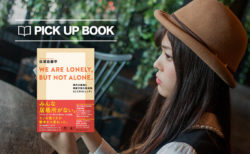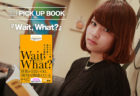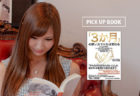こんにちは。ゲンゴローです。今回は『仕事2.0 人生100年時代の変身力』を読みました。
人の長寿化・企業寿命の短命化により、終身雇用は崩壊したといっても過言ではありません。「人生100年時代」と言われ、多様な働き方が議論される昨今ですが、自分は満員電車での通勤や長時間の残業、希望の通らない人事異動等、サラリーマンの悪しき習慣に日々悩まされており、今の働き方と将来に漠然とした不安を抱えています。
今後生き残るためには、今何をするべきなのか知りたい! そう思ったのが本書を手に取ったきっかけです。
本書では、人生100年時代を生き抜くために必要なスキルや心構えが具体的に紹介されています。その中から、自分の現状の変えるために今日から実践しようと思ったことを紹介します。
「仕事1.0」から「仕事2.0」へ
良い大学・良い会社に入って、言われるまま仕事をこなしていれば将来安泰という時代は終わりました。誰もが生涯現役として働き、時には所属する会社や職種も柔軟に変えていく意識と、そのために常に新しいことを学ぶ姿勢が必要です。
「教育→仕事→引退」と人生が3ステージだった時代の働き方を「仕事1.0」とすると、上記のような働き方を「仕事2.0」と本書では定義しています。
人生100年時代を生き抜くための読書術
「仕事2.0」の時代を生き抜くためには、日々本業以外の勉強、いわば「大人の学び」をすることが欠かせません。
本書では大人の学びとは「体験総量」を上げることだと説明しています。これは座学や知識の収集だけではなく、現場での実践や行動を通して経験を積み、成功パターンを「持論化」するということです。
たとえば副業や転職によって新たな分野の仕事を経験することも一つの手ですが、それには時間や労力がかかり、本業がおろそかになるリスクもあります。そこでおすすめされているのが読書による「代理体験」です。読書であれば、効率的かつ手軽に「体験総量」を上げることができます。
読書が「他人の経験を買う」行為であることを自覚し、本を読むことを通して他者の経験を「追体験」することが、読書を学びにする秘訣だと著者は言います。そこから得られた経験を、すぐに自分の思考や仕事に反映させることで、「◯◯とはこういうことか」といった成功パターンを「持論化」することができます。
また、読書による学習効果を高めるための方法として、東京大学経済学部教授の柳川範之氏の2つの極意が紹介されています。
①「ケンカしながら読むこと」
これは、本に書かれている内容に「本当は正しくないんじゃないか」「違う考え方もありうるのではないか」などと突っ込みを入れながら読むということです。そうすることで、その本を深く理解することにつながると言います。
「今の時代に求められている考える力とは、識者の話を鵜呑みにせず、自分で理論を組み立てて、違う理論を語れること。本の内容を何の疑いも無く、頭に入れているだけではほとんど何も残らない」と柳川氏は強調しています。
本を読んだだけで、つい分かった気になってしまうことは自分も良くあります。新しいことを学んだ時は、異なる作者の本も読むなどして、別の視点からも見られるようになることが大切ですね。そして学んだことを他の人に説明したり、ブログにまとめたりして、自分の言葉で再発信するクセをつけると、より効率的に学習が進められます。
②「熟成させること」
これは、たとえば歴史書の場合だったら、「この出来事と他の出来事につながりはないか」「他の分野に応用できないか」「共通するメッセージは何か」などの切り口で考えながら読むということです。
そうすると、時代や地域の違いを超えた「普遍的な構造」を見いだすことができます。この読書を介した「加工作業」こそが、現在や未来を生きる上で必要な知恵を得る勉強の本質だといいます。
ある一面からのみではなく、異なる角度からも考えることが大切だということですね。
上記を読んで、「ケンカしながら読むこと」「熟成させること」という読書法は、読書以外にも応用できるのではないかと思いました。たとえば、上司や他部署の社員など、自分と立場や考え方が異なる人から意見を聞くケースが挙げられます。
私は仕事柄、多様な研究分野の有識者のお話を伺う機会があります。自分が関心のある分野であれば、楽しく聞くことができるのですが、あまり興味の無い内容だとついつい聞き流してしまうことが多々ありました。
「ケンカしながら読む」「熟成させる」という視点を応用すれば、自分の言葉で語れるように意味を考えたり、他の事象と共通するメッセージを探し出して普遍的な真理を読み解いたりする思考の訓練になると思います。
今の働き方を見直すきっかけになる一冊
本書は自分の働き方を見直し、将来どんな働き方をしたいのか、そのために今何を学ぶべきか、どうやって学ぶべきか、について知ることができます。
働き方に正解はありません。個々でオリジナルの答えがあるはずです。
本書が、みなさんの働き方を見直すきっかけとなれば幸いです。