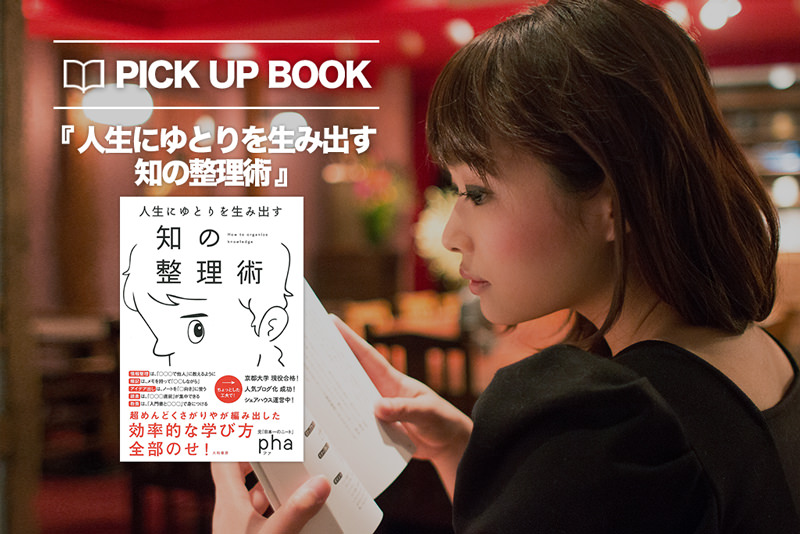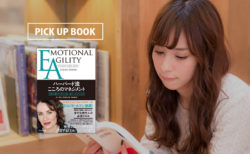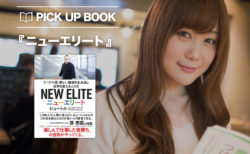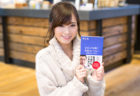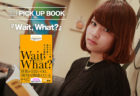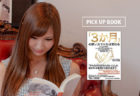春、始まりの季節。進学、就職、転職、そうでなくても心機一転、なにか始めてみよう! という人も多いのではないだろうか。私は読書を通して、新しい知識をどんどん学んでいきたいと思っている。
とはいえ、勉強を続けるのはなかなか難しい。あれだけやる気に満ちあふれていたのに、気づけば三日坊主になっていた。なんてことも、あったりなかったり…。
しかし今回紹介する『人生にゆとりを生み出す 知の整理術』の著者、phaさんは言う。
一生懸命、必死でがんばっているやつよりも、なんとなく楽しみながらやっているやつのほうが強い。
…がんばらなくていいの? 必死になるより、なんとなくやってほうがいいの…? 勉強を楽しむって…?
次々と「?」が浮かんでくるが、そんな疑問に応えるべく、手の内全部見せの勢いで、勉強を楽しむためのテクニックを紹介してくれているのが本書だ。
元「日本一有名なニート」のphaさんは、できるだけ働かないことをモットーにしつつも、Twitter(@pha)のフォロワーは32,000人を超え、著書を何冊も出版されている人気者。
今回はそんなphaさんの教えの中から、学ぶうえでの根幹となる「インプット」に焦点を当てたい。インプットする上で大切な3つのステップに沿いながら、phaさんのテクニックを紹介していく。
- まずは「興味を持つ」
- 「知識をかきまぜる」ように読む
- 「牛の消化」みたいに覚える
これで今年は挫折知らずになれる…はず!
1.まずは「興味を持つ」
ここ、意外に盲点ではないだろうか。人間、興味がないことにやる気は起きない。やる気が起きなければ、勉強しようと机に向かってみても、ダラダラ。なにも手につかない。頭にも入ってこない。
そこで著者はまず、勉強したいテーマに興味を持つことからはじめよう、と提案する。しかし、言うは易し、行うは難し。興味なんてどうやって持てばいいのか。
①詳しい人をフォローする
まずは、詳しい人と親しくなること。周りにいなければ、ツイッターなどで専門家をフォローしてみることを勧めている。
「詳しい人」というのは、その分野になにがしかの面白味を感じているからこそ、自発的に学ぶことができた人たちだ。つまり詳しい人は、その分野の「何がおもしろいか」を知っているということだ。
興味を持つための第一歩は、詳しい人たちを観察し、おもしろポイントをつかむことにあるらしい。
②関連するマンガを読む
ふたつ目は、関連するマンガを読むこと。マンガはキャラクターやストーリーの力で入り込みやすく、その分野の雰囲気をつかみやすい。マンガがなければ、小説や映画、雑誌などを読んでみるのも手だ。
③専門用語を覚えてみる
最後は、専門用語を覚えてみること。専門用語を覚えると、その分野の雰囲気をつかみやすくなるそうだ。たとえば横文字が多かったり、略語が多かったり、特有の言葉遣いにはその分野の特徴がよく表れるものなのだろう。
最初は慣れなくても、使いこなせるようになると会話がどんどん楽しくなっていくという。
詳しい人とお近づきになったり、マンガを読んだり、独特の言葉を覚えたり。まずは、どうにかして楽しい! と感じられるようになることが、大きな一歩となるのだ。
2.「知識をかきまぜる」ように読むこと
なんとなくでも興味が出てきたら、次は本やネットから知識を得ていこう。しかし学生の頃の勉強のように、丸暗記しようとするする必要はない。
著者は言う。知識は、曖昧にしておくことが大切だ、と。
耳を疑う一言ではないだろうか。私は二度見(読み?)してしまった。知識は、正確さが大切ではないのか。
しかし著者の出した例を読んで、膝を打った。
- A 【夕暮れ時】 に 【A】 という地点で 【鳥】 に襲われる(だからそういうときは警戒しよう)。
- B なんかこういう感じの時間や場所は危険だ、なんか大きいものが動いたらとりあえず警戒しよう、など。
Aの場合、場所や時間、捕食者が限定されてしまう。そのため、ほかの場所、時間、捕食者の場合に応用できない可能性が高い。しかしBは、具体的でないかわりに、ほかの場面や時間を想定できる。
つまりBの記憶だと臨機応変に応用できるので、この虫が今後同じような危険に遭遇する確率は低くなると予想できるのだ。
勉強も同じらしい。
例えば勉強している分野について、1冊しか本を読まないとする。確かにその本に書かれている知識は、あますことなく得られるだろう。しかしこれでは、「A」と同じパターンに陥ってしまう。
勉強したことを応用して自分なりに使えるようになるには、さまざまな意見や幅広い知識に接して、知識をぼんやり記憶しておくことが大切なのだ。
知識を曖昧に取得する方法
では、どうしたら知識を曖昧に取得できるのか。
著者は新しい分野の勉強を始めるとき、最低3冊は本を読むようにしているらしい。その内訳は、雰囲気の違う入門書2冊とエッセイなどの読みもの1冊。3冊以上読むと、いい感じに知識がぼやけるという。
こうして「知識をかきまぜる」ように読むことを勧めている。
3.「牛の消化」みたいに覚える
興味も出てきて本も読み始めた。さあ、これからは得た知識を蓄積させていくフェーズだ。
覚える段階で大切なことは、繰り返し見直すことだという。牛が食べ物を消化するように、何度も反芻しながら記憶を定着させていくことがポイントなのだ。
そもそも「覚える」とは、短期記憶を長期記憶化させることだという。
…なんて簡単に言ってはいるが、勉強で一番心折れるのは、この段階ではないだろうか。
昨日頑張って覚えたのに、英語の小テストで単語が出てこない…とか。試験中に歴史の年号が、XX42年だったか、XX24年だったか思い出せない…とか。
きちんと記憶したはずなのに思い出せないというのが、けっこう辛かったりする。
そんな難関「覚える」だが、著者はいくつかのテクニックを紹介してくれている。特に気になった3つを紹介したい。
①ストックとフローを意識してノートをとる。
1つ目は、ストックとフローを意識してノートを取り、ちょこちょこ読み返すことだ。
まず、ストックとフローとはなんだろうか。
- フローとは、思いついたことをとりあえず書き留めること。
- ストックとは、書きためたフローを他人が理解できるように整理すること。
つまりフローを読み返しつつストック(ノート)をつくる、というプロセスを踏めば、効率よく復習できるということだ。
そして長期記憶化には、ノートを見直すことも重要だという。本来であれば、講義を受けなおしたり、本を再読したりすればベストなのだろう。が、いかんせん時間がかかる。しかしノートや読書メモを見返せば、1時間の講義も数百ページある書籍も5分くらいで見直せる。
短時間の復習を何回も繰り返したほうが、より記憶に定着しやすいようだ。
②自然と目に入るようにしておく
覚えるための2つ目のテクニックは、自然と目に入るようにしておくこと。目につくところに覚えたいことを貼る。ザ・定番の覚え方。
この「目につくところ」、今や壁とドアだけではない。じゃあ、ほかにどこがあるのか?
ツイッターである。著者はツイッターを活用しているらしい。
この場合、ピンポイントで「覚えたいこと」ではないかもしれないが、勉強中のテーマについてのアカウントをフォローしておけば、関連するツイートがタイムラインにジャンジャン流れてくる。ツイッターを開けば、関連する情報が自然と目に入り、記憶するのにも役立つということらしい。
またネット上の無数の情報から、おもしろいものをピックアップして紹介してくれる人を「キュレーター」というのだそうだが、そうしたキュレーターをフォローしておくと、ネットからの情報収集のスピードが違うという。
③読書メモを取る
そして最後に、読書メモを取ること。
メモを何度も読み返すことで、情報を頭に定着させる効果がある。またメモを書くことで、より内容を覚えやすくなるという効果も期待できるそうだ。
しかしすべての本に詳しいメモを取っていては時間がかかる。著者は、本を重要度やおもしろさによって4つの段階に分けているらしい。
- 重要度ゼロ。読書メモは取らないが、本を読んだことだけ記録。
- 重要度低。おもしろかった部分だけ引用しておく。
- 重要度中。本全体がおもしろくて、何ヵ所かのメモでは足りないとき。読書メモ専用のブログに投稿。
- 重要度高。「この本はすごい」「この本の内容を深く取り込みたい」「他の人にも、この本のよさを教えたい」というとき。ブログやツイッターに、他人に見せてわかりやすく解説した文章を書いてみる。
さて、ここまでで勉強の楽しみ方について、何となくでもつかんでいただけただろうか。この本にはほかにも、アウトプットの方法や、だるいを解消するモチベーションや計画の立て方など、「phaさんそんなに教えちゃって大丈夫?!」と思ってしまうほど、さまざまなテクニックを大盤振る舞いしてくれている。
「そろそろ本気出したい」あなたへ、おすすめの一冊だ。