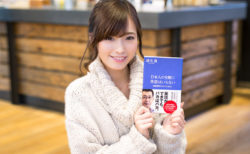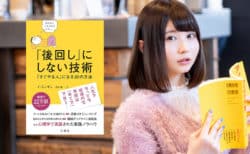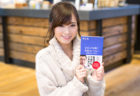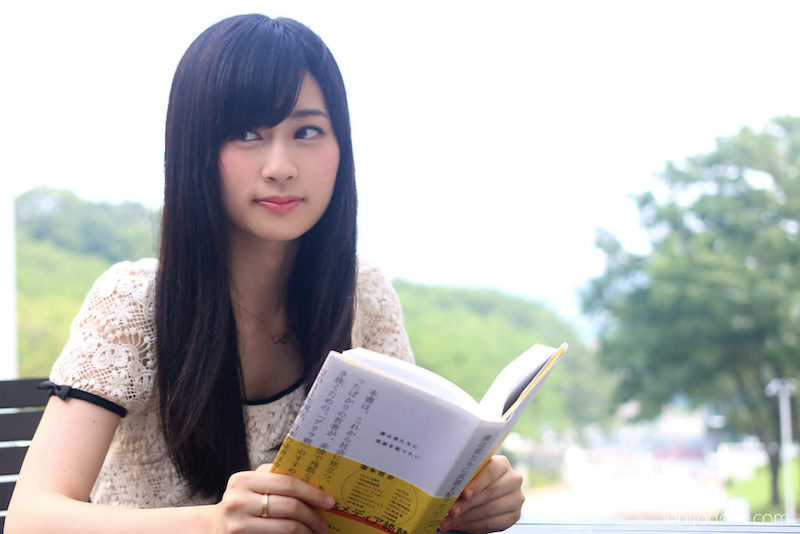
10秒でチェック!
- 資本主義経済では、誰でも身につけられるコモディティスキルだけでは差別化できず、賃金は最低まで買い叩かれてしまう。
- 他では代替できない価値をもった「スペシャリティ」な人材を目指す必要がある。
- 「自分の時間と労力、そして才能を、何につぎ込めば、そのリターンとしてマネタイズ=回収できるのか」という投資家的な発想が重要。
TOEICや資格は就職に有利にならない!
学生同士の会話で今でもよく耳にするのが、「就活に向けてとりあえず何か資格をとった方がいいかな?」というくだりです。
TOEICの点数や簿記のような資格は、自分のスキルを客観的に証明できるため、エントリーシートに少しでも書くことを増やしたいという思いで取得を目指す人もいるでしょう。
しかし「客観的に証明できるもの」というのは、つまり勉強をすれば誰でも習得できるものということです。
資本主義経済において、誰でも身につけられるスキル、つまり他で代替可能なスキルというのは、それ自体が差別化要素にはならないので、最低価格まで買い叩かれる運命にあります。
誰でもいいのなら、企業はコストを押さえるために、もっとも安い賃金で雇える人を採用するようになるからです。
もちろんそれらのスキルを身につけることが無意味というわけではありませんが、英語であろうと財務・会計の知識であろうと、誰もが身につけられるスキル「だけ」では、最終的には「安いことが売り」の人材になるしかないのです。
では、どうすれば「他では代替できない価値」を身につけることができるのでしょうか。
その方法を学ぶ上でおすすめの本が『僕は君たちに武器を配りたい』東大卒、京大准教授を務めながらマッキンゼー出身の投資家でもある瀧本哲史氏による、若者向けの人生指南書です。
本書は2012年の「ビジネス書大賞」作品ですが、本質を捉えた指摘は今でもまったく色あせることなく、将来の働き方に悩むすべての若者に読んで欲しい一冊です。
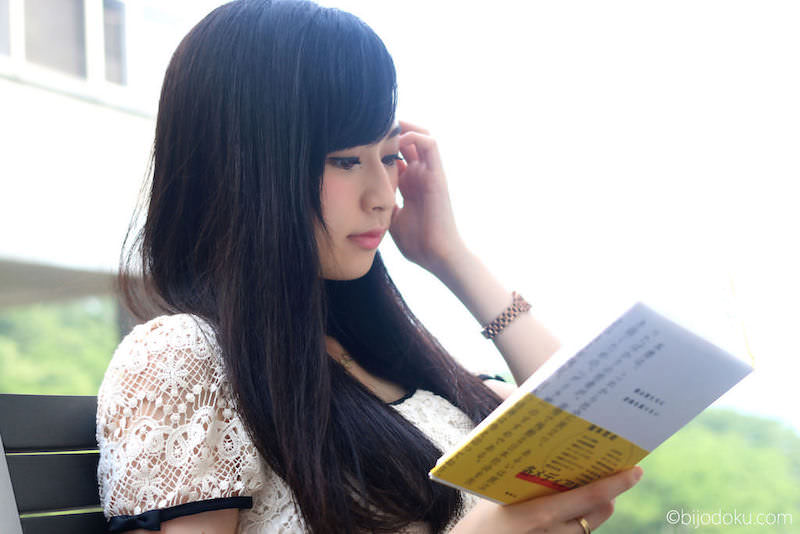
まずは資本主義の本質を理解しよう!
「他では代替できない価値」を身に付けるには、まず資本主義の仕組みについて理解することが重要です。
資本主義市場というのは、「商品が需要に対して不足しているとき」は値上がりし、「余っているとき」は値下がりするというのが根本ルールです。
どんな商品が余るのかといえば、差別化ができていないもの、つまり他と代替可能でどれを買っても変わらない「コモディティ商品」です。
コモディティは英語で「日用品」を指す言葉ですが、経済学の定義では「市場に出回っている商品が、個性を失ってしまい、消費者にとってみればどのメーカーのどの商品を買っても大差がない状態」のことを言います。
つまり、他で代替可能な「個性のないもの」はすべてコモディティで、これは労働市場における人材の評価についても同様のことが言えます。
英語や簿記、会計の知識などは、そもそもそれを勉強する人があまりに多いので、弁護士も、会計士も、税理士も「人余り」の状況になっています。
特に昨今は、海外の優秀で安価な人材に加え、技術革新が進んだことで、人でなければできない仕事はどんどん減っており、かつて高収入を得られた付加価値の高い資格もそれだけでは付加価値がなくなってきているのです。
商品にせよ人材にせよ、「他で代替可能」で「恒常的に商品が余っている状態」だと、資本主義経済では最低価格まで買い叩かれます。「コモディティスキル」だけでは、その職における最低価格帯の賃金で働き続けざるを得なくなるのです。
人より勉強をするとか、スキルや資格を身につけるといった努力だけでは、コモディティ人材から抜け出すことはできません。
「英語・IT・会計知識」の勉強というのは、あくまで「人に使われるための知識」であり、きつい言葉で言えば、「奴隷の学問」なのである。
今の学生たちが真剣に考えるべきは、「一生安泰な仕事はなにか?」「どうすれば大企業に入れるか?」ではなく、「大学を卒業後、どうやって自分の価値を、資本主義の世の中で高めていくか?」「コモディティ人材にならないためにはどうすればよいか?」です。

答えは「スペシャリティ」を目指すこと!
コモディティ人材から抜け出すためには、「他では代替できない価値をもった人材」になること、つまり本書で言うところの「スペシャリティ(Speciality)」になることです。
資本主義経済において「コモディティ」と「スペシャリティ」を分ける要素とは何なのでしょか。
簡潔に言えば、「明確にスペックを定義できるもの」、いわゆる「お勉強」で身に付くものはコモディティ化を避けられません。
一方で、「新たなビジネスモデルを作り出す」「大勢の人を率いる」といった、明確に定義できない力がスペシャティを構成する要素となります。
この点は「5年後に向けて今すぐ身につけるべき働き方の心構え3つ!」でも触れました。
では「スペシャリティ」とは具体的にどのような人材をいうのでしょうか。
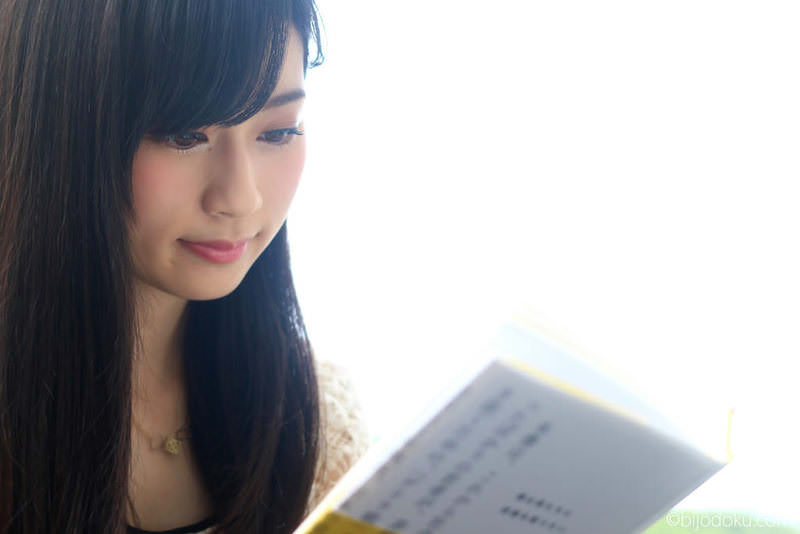
生き残れる「スペシャリティ」の4タイプ
本書では、「日本人で生き残れる4つのタイプ」として以下のものを挙げています。それぞれがどのような「他と代替できないスペシャリティとしての価値」を持っているのか注目しましょう。
1. マーケター
マーケターとは、「商品に付加価値をつけて、市場に合わせて売ることができる人」を言います。
自分のスキルや商品をコモディティのまま売りに行くのではなく、「ストーリー」や「ブランド」といった、一見とらえどころのない(つまりスペックを明確に定義できない)価値を作り、あるいは発見して、もっとも適切な市場を選んで商品を売る戦略を考えられる人です。
自分自身で何か画期的なアイデアをもっている必要はなく、「世の中で新たに始まりつつある、かすかな動きを感じ取る感度の良さ」と、「なぜそういう動きが生じてたのかを正確に推理できる分析力」が重要です。
個人の働き方においても、マーケティング的視点を持てるかどうかが「稼げる人」と「稼げない人」を明確に分けます。
資格や専門知識それ自体よりも、そのスキルを市場が求めているかたちで売ることができるマーケティング力が必要なのです。
2. イノベーター
2人目は、「まったく新しい仕組みをイノベーションできる人(=イノベーター)」です。
「イノベーション」と聞くとなにか特別な才能をもった人だけが生み出せるもののように捉えられがちですが、本書では「努力次第で誰でも伸ばすことができる力」だと言います。
なぜなら、イノベーションとは「既存のものを、今まで違う組み合わせ方で提示すること」がその本質で、まったく新しい製品をゼロから生み出す必要はないからです。
いろいろな専門技術を学び、その組み合わせを変えることや見方を変えることが、イノベーションを起こす素地になります。
そして、そのチャンスは「今現在、凋落しつつある大手企業の周辺」に眠っていると言います。
例えば、インターネットの登場によってテレビ業界の凋落が叫ばれていますが、「人々が日々の情報を映像と音声で得たいというニーズ」は普遍的でなくなることはないので、そこにはイノベーションのチャンスがあると言えるからです。
その業界で「常識」とされていることを書き出して、ことごとくその反対のことを検討してみましょう。

3. リーダー
3人目は、「自分が起業家となり、みんなをマネージ(管理)してリーダーとして行動する人(=リーダー)」です。
リーダーに求められる資質は、世の中にいる大多数の「凡人」をうまくマネジメントして、「あまり給料を払わずとも、モチベーション高く仕事をしてもらうように持っていくこと」です。
また、優れたリーダーには「自分はすごい」という勘違いと、宗教家のような確信に満ちた態度が必要だと言います。
革命的なことを成し遂げるには、多くの社員を先導していく必要があり、そのためには自分が信じ込んでいるビジョンやストーリーを伝えてアジテートしていける、新興宗教の教祖のような強烈な存在感が必要だからです。
そして、成功するリーダーは過去にコンプレックスを持っていることが多いと言います。コンプレックスを払拭したいと言う思いが事業を成長させる強い原動力となるからです。
もしあなたが大きなコンプレックスを抱えているとしたら、それはリーダーになる大切な素養を持っているということなのかもしれません。
4. インベスター
最後は「投資家として市場に参加している人(=インベスター)」です。
本書で繰り返し述べられているのが、「これからは投資家的な発想を学ぶことがもっとも重要だ」という点です。
投資家的な発想とは、何も株主になれということではなく、「自分の時間と労力、そして才能を、何につぎ込めば、そのリターンとしてマネタイズ=回収できるのか」を真剣に考えて生きるということです。
なぜなら、「資本主義の社会では、究極的にはすべての人間は、投資家になるか、投資家に雇われるか、どちらかの道を選ばざるを得ないから」です。
投資家的な立場にいれば、自分の時間や労働力を大きなリターンに変えられる可能性があります。しかし、投資家に雇われる側(つまり単純労働の従業員)では、できるだけ安く買い叩かれた一定の給与で働かざるを得なくなります。
投資家的な観点からすると、「就職して一生サラリーマンの未知を選ぶ」というのもハイリスクな選択です。
サラリーマンとは、ジャンボジェットの乗客のように、リスクを取っていないのではなく、実はほかの人にリスクを預けっぱなしで管理されている存在なのである。つまり、自分でリスクを管理することができない状態にあるということなのだ。
自分の時間や労働力の投資をリターンに変えられるポジションに身を置きながら、自分でリスクを管理できる働き方をすることが重要なのです。
注意したいのは、著者は「これら4つの中からどれかひとつのタイプを目指せ」と言っているわけではないということです。望ましいのは、「一人のビジネスパーソンが状況に応じて、この4つの顔を使い分けること」です。

まとめ
本書では、優秀な人はビジネスを作る側へ行くべきだと言っていますが、学生起業については反対の立場を取っています。
社会の仕組みやビジネスの構造を理解しない状態で起業してみても、「コモディティ会社」を作ってしまう可能性が高いからだと言います。
自分が起業したい分野の会社に一度就職して、その業界のコモディティとスペシャリティを分ける要素は何かを学んだ上で起業した方が、うまく行く可能性が高いということです。
この点については「別に会社で学ばなくても、起業してから学べばいい」という意見もありますので、両者のメリットデメリットを自分の頭で考え抜いた上で、納得のできる道を選ぶようにしましょう。
合わせて読みたい
モデルプロフィール
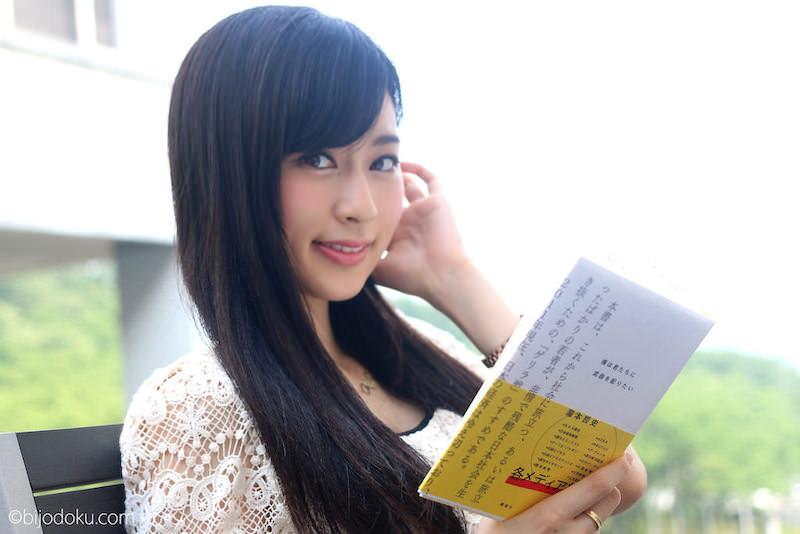
・名前 :色紙悠
・生年月日 :1994.9.9
・出身 :東京都
・職業 :大学生
・将来の夢 :何事も両立できて、しっかり自分を持った理想の女性
・ブログ :「色紙悠オフィシャルブログ」
・ミスコン投票はこちら!
本日のおまけ