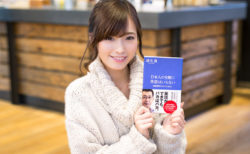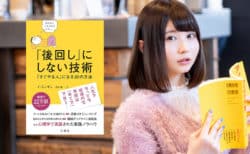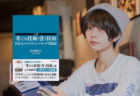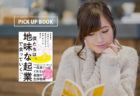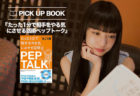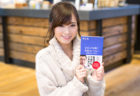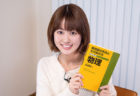起業の成功率を高める実践的手法とは?
起業コストが下がったことで、誰でも起業にチャレンジできる環境が整ってきました。しかし、それによって起業の成功率が高まるわけではありません。
むしろ、母数が増えることで失敗の数も増えており、華々しく成功した一部のスタートアップの陰に数え切れないほどの失敗が転がっているのが実状でしょう。
どうすれば起業の成功率を高めることができるのでしょうか。
今回は、ムダを減らすことで起業の成功率を高める実践的な手法を記した、エリック・リース著の『リーン・スタートアップ』を紹介します。
本書は2012年に発売され、日本でも大きな注目を浴びた一冊ですが、ピーター・ティール著の『ZERO to ONE』では、「リーンスタートアップ」に否定的な見解が記されています。
しかし両著を読んでみると、決して双方の主張が矛盾するものではないことに気づきます。ティールはリーン・スタートアップを「計画を重視しない起業手法」として否定していますが、エリック・リースは「計画が不要」とは説いているわけではないからです。むしろ「とにかくやってみよう」といった「just do it」型起業はうまくいかないと断言しています。
「リーンスタートアップ」は古びた手法でも間違った方法論でもなく、すべての起業家が理解しておくべき重要なコンセプトだと思います。

“リーン・スタートアップ”ってどういう意味?
リーン(lean)とは「痩せた、引き締まった」という意味の単語で、リーン・スタートアップとは端的に言えば「無駄を排した」起業手法です。
ここでいう「無駄」とは、予測ができないことを正しいと思い込んで計画を立て、実行する過程で発生する「やらなくてもよいこと」です。
不確実性が大きいスタートアップでは、そもそもどういう人が顧客になるのか、どういう製品を作るべきかさえもまだ分からないことが多いもの。にもかかわらず、思い込みで複雑な計画を立て、その実行のために多大な時間と労力を費やしてみても、「誰も欲しがらないモノ」を作ってしまう可能性が高いのです。
もちろんこうした失敗から学ぶこともありますが、「その学びを得るためには、本当にそれだけの時間と労力を投資する必要があったのか?」については真剣に考える必要があるでしょう。
リーン・スタートアップとは、この「学び」を得るためのムダを最小限に抑え、得られた学びによって改善を繰り返し、ビジョンを実現するための起業手法なのです。
そのためには、まず「本当に作るべきモノー顧客が欲しがり、お金を払ってくれるモノ」を突きとめることが重要です。
ここでポイントとなるのが「検証による学び」と「実用最小限の製品(MVP)」という考え方です。

1. 検証による学び
「検証による学び」とは、ビジネスの要となる仮説を検証する中で「顧客が本当に望んでいるモノとは何か」を学び、それを元に製品を改善していこうという考え方です。
スタートアップが行うことはすべて検証による学びを得るための「実験」だと考え、そこで得た学びを製品に生かしていくのです。
例えばあるビジネスアイデアを思いついて、すぐにでも作れる状況にあるとしても、「それが作れたら顧客は買ってくれるのか?」「どれくらいの顧客が買ってくれるのか?」が検証されていない状態で大量の予算と人材を投資してしまうと、結果的に仮説が間違っていた場合、それまでの苦労の多くがムダに終わってしまいます。
ビジネスの要となる仮説を検証するということは、つまり「この製品を作るべきか」という問いの答えを得ることです。
このとき必要なのは「完璧な仕上がりで美しく、どこに出しても恥ずかしくない製品」ではありません。なぜなら、誰が顧客なのかが分からなければ、何が完璧であるかも、何が品質なのかも分からないからです。
必要なのは、「必要最低限の機能を整えた製品(Minimum Viable Product:MVP)」です。

2. MVPの制作
「必要最低限の機能を整えた製品(MVP)」をリリースして顧客からフィードバックを得ることで、「そもそもその製品にニーズはあるのか」を検証します。
検証すべきは「価値仮説」と「成長仮説」。この2つの仮説を検証するために「必要最低限な」機能を整えた製品を作るということです。
価値仮説とは「顧客が使うようになったとき、製品やサービスが本当に価値を提供できるか否かを判断するもの」、成長仮説とは「新しい顧客が製品やサービスをどうとらえるかを判断するもの」です。
例えばフェイスブックがサービススタートしたとき、まだ一部の大学でしか使えなかったものの、アクティブユーザーがサイトで過ごす時間は極めて高く、ユーザーの半数以上が毎日アクセスしていたと言います。
これは顧客がフェイスブックに価値を感じていたことを示すのに十分な数値であり、「価値仮説」についての裏付けがあったと言えます。
また、そこから大学キャンパスへの普及速度も驚異的に速く、2004年2月4日にサービス開始してから、2月中にはハーバードの学生の4分の3近くが使うほどだったことから、「成長仮説」も検証済みだったと言えます。
この2つの仮説を検証することが、スタートアップの成功率を高めるために大いに役立ちます。
「必要最低限の機能を整えた製品(MVP)」は、必ずしも実際にリリースされる製品の形を整えている必要はありません。
たとえばDropboxの場合、実際に利用できる製品を公開する前に、「どんな製品なのかをわかりやすく伝える動画」を制作し、「開発中の製品を顧客が欲しがるか」を検証しました。
この動画が「MVP」の役割を果たし、多くの顧客が実際に予約するという形で、「優れた体験を提供できれば顧客は我々の製品を使ってみてくれるのか」という問いに対する裏付けがとれたというわけです。
従来の製品開発は長い時間をかけてじっくりと開発し、完璧な製品をめざすが、MVPは目的が学びのプロセスを始めることであってそれを終えることではない。プロトタイプやコンセプト検証と違い、MVPは製品デザインや技術的な問題を解決するためのものではない。基礎となる事業仮説を検証するためのものなのだ。

3. 革新会計
スタートアップアップにおいて、検証による学びを実現できているかどうか、事業が前進しているかどうかを確認するには、従来の会計手法と異なる方法が必要です。
なぜなら、不確実性が高いスタートアップにおいて一般的な管理会計を当てはめてみても、事業の将来性を正しく見抜くことはできないからです。
例えば赤字が続けばその事業はうまくいっていないと評価すべきなのか、製品が計画通り作られていれば(それが求められていない機能であっても)順調な進捗と言っていいのかのように。
ここで必要なのが「革新会計(イノベーションアカウンティング)」です。
革新会計を活用すると、「持続可能な事業にする方法を学んでいる」と客観的に証明することができます。
まずは、ビジネスの要となる仮説から定量的な財務モデルを作り、将来的に成功したときどのような事業となるかを推測します。
その理想状態に向けて「成長の原動力」となるポイントについて、適切な学びを得て、その学びを効果的に利用できているかどうかを評価の基準とするのです。
事業によって成長の原動力となるものは大きく異なるが、同じ枠組みでリーダーを評価し、その責任を問うことができる。

4. 方向転換(ピボット)
革新会計によって理想状態に向かって進めていないと判断された場合、現状の戦略を根本的に見直して、新しい戦略的仮説へと方向転換する必要が出てきます。
これを「方向転換(ピボット)」と言います。
当初の戦略から方向転換するか、維持するかはリーダーにとって極めて難しい決断ですが、持続的な成長を実現させるためには避けては通れない問題です。
方向転換するならすべてのプロセスをやり直す必要があり。新たなベースラインを設定し、そこからもう一度エンジンをチューニングしていかなければならないのだ。
ピボットの型は一つではありません。例えば、それまで機能の一つだと考えていた点に集中する「ズームイン型ピボット」や、製品の機能を変えることなくオーディエンスを変える「顧客セグメント型ピボット」など、本書では10のパターンが紹介されています。
当然、事業の内容やそのとき得られている学びによって採用すべき型は異なります。
ピボットとは、単に変化を勧めるものではない。製品、ビジネスモデル、成長のエンジンに関する根本的な仮説を新たに策定し、それを検証できる構造の変化をピボットと呼ぶのだ。
著者は、ピボットこそ「リーン・スタートアップ方式の肝だ」と言います。なぜなら、ピボットがあるからこそ、失敗から立ち直ることができるからです。
まとめると、これまで見てきた「(MVPの)構築-(革新会計による)計測-(検証による)学習」のフィードバックループをできるだけ早く回すのがリーン・スタートアップの考え方であり、押さえておくべき要点なのです。
モデルプロフィール

・名前 :齊藤一美
・生年月日 :1986.12.18
・出身 :北海道
・職業 :会社員
・Twitter :@kaaaaami1218
ご協力いただいたお店

店名 :Tabela(タベラ)
住所 :東京都渋谷区宇田川町37-18
TEL :03-6825-5501
営業時間:平日 11:45~23:00
土日祝:12:00~23:00
定休日 :年末年始
本日のおまけ