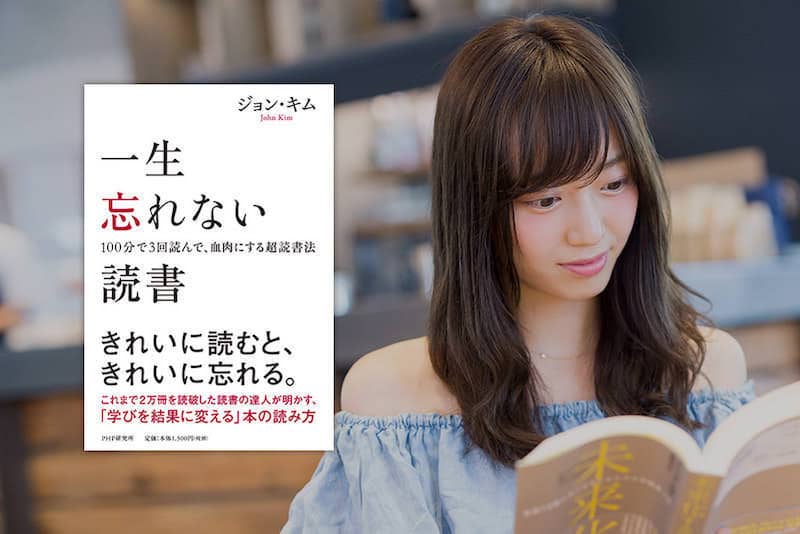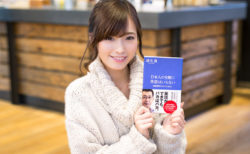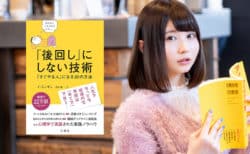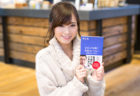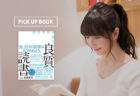「せっかく本を買っても、結局読まずに終わってしまう」「読んだとしてもすぐに内容を忘れてしまう」「1冊を読み切るのに時間がかかるので、なかなか読む気になれない」──こうした悩みから読書が習慣にならない人は多いと思います。
スマホで今すぐ楽しめるコンテンツが増えたこともあって、読書の優先順位が下がり、本を読む機会自体が大きく減っている人も多いでしょう。
読書の重要性は依然として変わりませんが、1つのことに費やせる時間が減ってきている今、いかに時間をかけずに本(とりわけビジネス書)の要点を理解し、記憶し、実際の仕事や生活に生かしていくかが重要になっています。
趣味の読書であれば効率を考える必要はありませんが、ビジネス書は、仕事での成果を上げるために読む人がほとんどでしょう。そのためにかける時間は短ければ短いほど効率がよく、生産性が高いということになります。
そこでお勧めしたいのが、ジョン・キムさんの、『一生忘れない読書 100分で3回読んで、血肉にする超読書法』です。
本書で紹介されている「100分で3回読む」という読書法を知ると、本を読むスピードが格段に上がるだけでなく、これまで以上に本の内容を理解し、記憶できるようになります。
以下、「100分で3回読む」読書術の方法をご紹介します! 1冊読み切るのにものすごく時間がかかり、読み終えた頃には内容を忘れている、という人は、ぜひ参考にしてください。
なぜ「100分で3回」なのか?
そもそも、なぜ「100分で3回」読むべきなのでしょうか。これは時間をかけて1回通読するよりも、100分で3回読んだ方が、多くの効能を得られるからです。
以下、5つに分けてご紹介します。
①「読書の目的」を果たすため
ビジネス書や教養書を買う場合、そこには「自分の人生や仕事に役に立たせたい」といった目標・目的があるはずです。
しかし多くの人は、2週間かけて1回読んだ本のことを、読み終えた後にきちんと覚えていませんし、その内容を人に語ることもできません。
せっかく時間をかけて読んだのに、すぐに忘れてしまっては「読書の目的」を果たしているとは言えません。読むこと自体を目的にするのではなく、目的を果たすために読書をすると考えるべきです。
キムさんの勧める「100分で3回」の読書術は、本の構造を理解した上で、目的に適うポイントだけを的確に見つけ出すように読むので、まさに目的を果たすための読書ができます。
「100分で3回」読むためには、そもそも一冊を丸々読み切ることはできません。読むべき箇所を明確にして、読む必要のない箇所を思い切って切る姿勢が必要です。
「読むべき箇所」とは、「読書の目的」があるからこそ決まります。目的を定めれば、それを果たすために必要な箇所だけを効率的に拾い読みできるようになります。
②「集中力」を高めるため
「100分で3回」と制限を設けることで、緊張感が生まれ、集中力が高まります。短時間で読むと決めると、没入して読めるようになるので、高い集中力で読み進められるのです。
これは実際にやってみると、その効果を実感できます。タイマーが刻一刻と減っていく状況で、目的に適う情報を「探す」ように読むと、自然と集中力が高まり、高い情報処理能力を発揮できるのです。
多くの人は「本はじっくりゆっくり読むのがよい」と思い込んでいるため、読書に時間制限を設けることをしません。しかし目的を達成するための時間は「短ければ短いほど効率がよい」ので、時間制限を設けることは理にかなっています。
「時間をかければ効果が上がる」と思い込んでいる人は多いかもしれませんが、実は逆で、時間をかけることは、時間に対する緊張感がないこと、目的が曖昧なことを意味しているとキムさんは指摘します。
締め切りがなければ、仕事はいつまでも終わりません。時間制限をつけることで緊張感が生まれ、時間に合わせて読むようになります。
時間と成果に対する関係性について、根本的なマインドをシフトさせましょう。
といっても、短時間で一度読むだけでは、本質を捉えられないし、記憶にも残りません。だから「反復」が重要になるのです。
③「記憶」に残りやすくするため
人は一度読むだけでは確実に忘れてしまいます。人間の記憶力を過信してはいけません。
そこで「3回読む」という反復が力を発揮します。反復することで記憶に焼き付けることができます。
これもやってみるとわかりますが、1回目よりは2日目の方が、2回目よりは3回目の方が、確実に理解は深まり、記憶できます。ただし、キムさんの経験上、3回目と4回目ではさほど差が出ないそうです。だから「100分で3回」がもっとも効率のよい読み方なのです。
「100分で3回読み」を実践すると、時間をかけて読んだときよりも、ポイントをはっきり捉えられることに気づくでしょう。
「かけた時間」ではなく「読んだ回数」が、より記憶力と理解力に影響を与えてくれること、また時間をかけるほどポイントが見えづらくなり、理解度が低くなることに気づくと、割り切って読み飛ばしができるようになります。
2週間かけて読んだけど、2週間後にはほとんど覚えていない読書と、時間も節約できてポイントもつかめるよになり、それだけを覚えておけばいいという読書、どちらが有効か、言うまでもないでしょう。
④「習慣化」するため
1冊にかける時間が短ければ短いほど、習慣化、システム化しやすくなります。日常的に実践するハードルが下がるからです。
「100分で3回」の読書法は、1回目が10分、2回目が50分、3回目が40分という時間配分で読みます。もちろん100分ずっと通しで読む必要はなく、スキマ時間をうまく使うことが勧められています。
たとえば、朝1時間早く起きて、その時間を「1回目」と「2回目」の読書に充て、仕事を終えて、家に戻ってきてから「3回目」の読書をする。もしくは行きの電車の30分、帰りの電車の30分、あとは昼休みの40分で10分の時間を確保する。
1日100分が難しければ2日で100分でもいいし、3日で100分でも、1週間で100分でもOKです。
「1冊読んでみましょう、その時間を確保しましょう」となると難しく感じる人でも、「100分の時間を確保してみましょう」であればできるはずです。
このように一連のプロセスと制限時間が決まっていた方が、習慣に組み込みやすく、結果として習慣化しやすくなります。
先に時間を確保してしまうこと。これこそが習慣化の要だとキムさんは言います。1週間の中で、どこで「1回目」をやり、「2回目」をやり、「3回目」をやるのかを決めてしまいましょう。
⑤「多読」するため
1冊にかける時間を「100分」と制限することで、より多くの本を読むことができます。
キムさんは「より多くの本を読むことが大事」だと考えており、本を読む時間を増やすよりも、読む冊数を増やすことを心がけてほしいと述べています。
本は、著者が人生で得た教訓を千数百円で手に入れることができるものであり、これは極めて贅沢なこと。多読することで、もっといろんな世界を体験できるようになり、もっといろんな素敵な本に出会う可能性も高くなります。
数をこなすためには、短時間で効果的に読む術を手に入れる必要があります。それが「100分で3回読む」ことであり、この読書法を実践んすると、読書の効能をより多く得られるようになります。
また短時間で本質、ポイントをつかむ読書ができるようになれば、「この本はそれほど自分の役には立たないかもしれない」という本もすぐにわかるようになります。無駄な本に時間をかけないことで、自分の人生に大切な価値を与えてくれる本に多くの時間を使えるようになります。
このように「100分で3回読む」ことにはたくさんのメリットがあり、多くの効能を得られる読書術だと言えます。
「100分で3回読む」戦略的読書術
それでは「100分で3回読む」読書術のやり方を紹介しましょう。
1回目─全読み(10分)
「1回目」は10分で全体にざっと目を通し、本の構造を把握します。
大まかな構造で、どこで何を言おうとしているのか理解して読むのと、どういう構造の本になっているのかわからず著者に引っ張られていくのとでは、理解度が大きく異なります。構造を理解することで、著者が最も伝えたいコアメッセージにも気づくことができます。
まずは目次を見て、それから本文を軽く10分ほどかけてパラパラと読んでいき、全体を把握していきます。読むというよりも、「スキーミング」をしてどこを読むべきかを決める作業です。この輪郭把握と順位づけによって、「2回目」における時間配分が大まかに決まっていきます。
「1回目」では、理解度は低くても10分で読めるという感覚を手に入れることが重要です。8割を捨てるくらいの気持ちで読みましょう。
読むのではなく、探すイメージ。目的に適う重要な部分を探しに行かなければならないと考えると、むしろ飛ばさないといけないことに気づきます。そもそも本のすべてを記憶することなどできないので、目的に適う内容でない箇所はバッサリと捨てながら読んでいけばよいのです。
先に「読書の目的」を定めることが重要だと話しましたが、その本によって何を得たいのか、自分はどんなアウトプットを得るために、この本を読むのかといった「本を読む目的」が明確であるほど、優先順位がはっきりし、スキーミングは有効になっていきます。
また一度、最後まで行った感覚を得ると「この本はこのくらいだ」と自分の中でつかめるので、その後の配分がしやすくなります。
向かう時には限りなく長くかかったと思える道のりが、帰ってくる時にはそうでもなく感じるように、目的地までの距離をつかめているかどうかで、精神的負荷は変わってきます。1回目に最後まで目を通して、全体像を把握しておくことの意味はここにあります。
2回目─本読み(50分)
「2回目」の50分は「本読み」、詳細を含む理解のための読書です。
スキーミング読みでポイントを理解した上で、マーカーを片手に読み進めていきます。気になる箇所には、黄色いマーカーで線を引きましょう。
まだ深読みをする必要はありません。時間は50分しかないので、すべてを散策的に読んだり、ゆっくり立ち止まったりすることはせず、「1回目」でここぞ、と狙ったところだけを読んでいきます。
すると強烈な集中力が発揮されます。1回目のスキーミング読みは、2回目の「本読み」の際の時間配分を決めるためにあると言えます。
重要なのは、決まった時間ですべてを回ってみることです。この点について、本書に非常にわかりやすい例が記されているのでご紹介します。
あなたが200人規模のパーティに行ったとしたら、どのようにして参加者と会話をし、関係を築こうとするでしょうか。最初に顔を合わせた3人と最後まで話をし続けるということは、まずないでしょう。全員と1分ずつ話す、というのも現実的ではありません。
最初の10分ほどは、全体を把握するためにスキーミング(どこにどんなグループがあるのか、どんな人が来ているのかを確認)することから始めるのではないでしょうか。その後、いくつかのグループを回ってみて、最終的に一番興味のある、学びのあるグループや人と重点的に関わり、次に繋がるように会話を深めたり、名刺交換やSNS交換などをするはずです。
これが、本書の読書術にそのまま当てはまります。1回目にスキーミング読みで構造をつかんでから、2回目で章ごとに回ってみて気になる部分をチェックし、3回目に学びのある章やページ、メッセージを重点的に読んでいく、ということです。
パーティで自分にとって必要な人と知り合い、関係を築くための方法を考えれば、「100分で3回」の読書法の有効性がわかると思います。
全体を見渡し、詳細を見極める。これが50分の「本読み」においては特に重要です。
線引きのための本読みが終われば、「3回目」の深読みに入ります。
3回目─深読み(40分)
10分の「1回目」が全読・スキーミング読み、50分の「2回目」本読みに次いで、「3回目」は40分の「深読み」です。
スキーミング読みで構造を把握し、本読みで全体像を把握し、「3回目」ではより深く読んでいきます。3回読むと、本の構造が頭の中に刻まれ、理解度が大きく変わります。すると本の内容について語れるようになります。これが反復の効果です。
「3回目」は、1回目でつかんだ構造、2回目で読んで線や黄色いマーカーを引いた箇所を意識して、今度は赤(ピンク)のマーカーを引き、必要に応じてメモも書き込みながら読み進めていきます。
「2回目」で黄色いマーカーを引いた箇所を重点的に読み、その中で、特に重要だと思うところにさらに赤(ピンク)のマーカーを引いていきましょう。これを「3回目」の深読み40分のうち、10分を使って完了させます。
その後、赤でマーキングしたところを中心に、残りの30分を使って読んでいきます。読んでいくというより、書いていきます。これは大事だという内容を、別のペンで本にメモしていくのです。
キムさんは「アウトプットこそが、最強のインプット」だとして、本を読むときには、必ずアウトプットをすることを勧めています。それもわざわざ読書ノートにまとめずに、本にそのままアウトプットすることを勧めています。
書き込む内容はなんでもOK。まずは気になるフレーズなど、同じ内容を写し書きするだけで構わないので、ページ内の空いた白いスペースにメモを書き込んでいきます。
加えて「ここは大事だ」というページに、自分が感じたこと、思ったこと、浮かんだことなどを書き込んでいきます。著者が書いていることに対して、自分の感想、意見、言い換えの言葉、著者への質問などを書き込むのです。
こうすることで、ただ著者から情報を受け取るだけではなく、著者と一緒に考えを深めていく、共作を作るような読書をすることができます。
本の内容を踏まえてメモを書くという行為は、本の内容を理解しないとできません。理解した上で、さらにそれを表現していくことになるので、理解は完全に自分のものになります。
メモを取り、手を動かすことは、後からそれを見て読み返せる、という以前に、理解度においても大きな効果があるのです。
また本を改めてめくってみたとき、その本が自分のものになった実感が湧くようになるため、単なる読書、単に知識を得ただけの読書とは、まるで違う手応えが得られるようになると言います。
もちろん本当に良書だと思えば、「4回目」、「5回目」読みをしてもOKです。そうすれば、さらに理解は深まるはずです。
とにかく「100分で3回」を実践してみよう
キムさんは、とにかく「100分で3回」と決めてやってみることを勧めています。それが正解かどうか気にすることなく、まずはやってみてください。
人は、決められたフォーマットが決まっていれば必ずできますが、裁量権を与えられると逆に苦しくなります。だから「10分、50分、40分」というフォーマットを持ち、そのまま従うことが重要なのです。
最初は時間制限の中で思うように本が読めず、慌ててしまうかもしれません。しかしそれでもやってみると、長い時間で1回読むよりも、短い時間で3回読んだほうが、はるかにポイントをつかめるということに気づくはずです。
そういう感覚が得られ、成功体験になると、もっと前向きになれます。そのうちに慣れてきて、「100分という限られた時間で、いかに目の前の本から自分の目的を果たす答えを見つけられるか」という視点で本を読むようになるでしょう。
まずは本書のフォーマットに沿って読んでみることから始めてみてください。