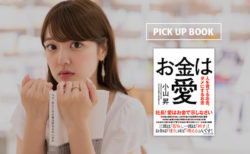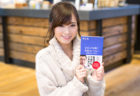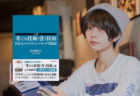こんにちは。志織です。近年「働き方改革」を進める企業が増えてきています。その背景には、次の2つの要素あるのではないでしょうか。
- 人口減少や少子高齢化などによる労働力の減少
- 働き方の多様化に対するニーズ
これらの課題を解決するために「働き方改革」が必要とされており、そのアプローチ方法の一つとして考えなければならないのが「生産性の向上」です。
私自身、会社員として働いている中で、非効率な業務、無駄な業務が多くあると感じています。会社からも生産性向上に取り組むよう日々いわれており、自分でも残業を減らして自分の時間を増やしたいと思っているのですが、正直「どうやって?」「何から始めればいいの…?」と思っていました。
そのような状況で、『カイゼン・ジャーニー たった1人からはじめて、「越境」するチームをつくるまで』を読み、業務改善のためのヒントを多く得ることができました。
「カイゼン」というと、主に製造業で活用されるビジネス戦略だと考える人は多いでしょう。しかし「カイゼン」は、現場が中心になって業務改善を行なっていく手法のことで、より効率的により高品質の製品・サービスを生み出したいという想いが基礎になっています。そのため製造業以外の業種にも活用できる手法なのだそうです。
本書は、特に若手ソフトウェア開発者を対象に書かれていますが、そこで紹介されている取り組み(プラクティス)はどのような仕事であっても参考になるものでした。(私自身、ソフトウェア開発の仕事ではありません)
主人公とともに「カイゼン」を学んでいく
本書では、ITエンジニアの主人公がさまざまな問題に直面し、周りの人の助言をもとに工夫・努力を重ね、人間的に成長していくストーリーが描かれています。またストーリーと並行して、主人公の工夫や手法が理論として解説されています。
ストーリーがあるおかげで、それぞれの取り組みを具体的な背景や状況と合わせてイメージすることができ、さらに理論的な解説があることで読者の理解を促し、実践しやすくしてくれています。
第1章では、一人から始められるプラクティスが紹介されています。たとえば、もやもやを感じたら、まずは外にとび出してみること、業務の振り返りや「見える化」を行なってみることなどです。
主人公が会社を変えたいと色々な工夫を試みた結果、仕事をうまく回せるようになり、仲間を見つけ、社内勉強会というイベントを大成功させます。
そして第2章では、主人公がプロジェクトのリーダーとなり、たくさんの壁に直面することになります。ここでも主人公は持ち前のアツさと周りの助けや様々な工夫により、チームをまとめ上げていきます。
最後の第3章では、チームの枠を超えて社内外のあらゆるステークホルダーを巻き込んで奮闘し、プロジェクトを成功させていく様子が描かれています。
すぐに実践できる業務改善ノウハウ
この本の最大の特長は、現場の人間がすぐに実践できる取り組みを扱っているところだと思います。特に私が参考になると思ったのが、第1章で挙げられている「一人からはじめられる業務改善の手法」です。
たとえば「業務の見える化」では、まずはタスクレベルで「見える化」することが業務改善の第一歩になります。次にそのタスクを「重要度」「緊急度」の二軸でマッピングしていくことで、何に注力すべきで、どの業務を減らすべきなのかを明確にします。
また業務の進捗を振り返る上で、タスクマネジメントが簡単にできるようになる「タスクボード」も日々の業務に有用です。タスクボードとは、タスクを未着手(TODO)、着手中(DOING)、完了(DONE)に分けて、ホワイトボードや模造紙上で管理していく手法です。
第2章では、WhyやHowを明らかにする「インセプションデッキ」の作成手順、共通認識を育てる「ドラッカー風エクササイズ」、チームの強みを明らかにする「星取表(スキルマップ)」の作成方法が紹介されており、チームでプロジェクトを行う人にとって、大いに役立つだろうと感じました。
ちなみに「インセプションデッキ」とは、メンバー全員の共通認識を形作るために、プロジェクトのWhyやHowを明らかにしながら、プロジェクトの目的や背景、方向性、制約についてまとめたドキュメント(表)のこと。
「ドラッカー風エクササイズ」とは、「自分は何が得意なのか?」「自分はどうやって貢献するつもりか?」「自分が大切に思う価値は何か?」「チームメンバーは自分に何を期待していると思うか?」という4つの質問を通じて、メンバー間の期待を擦り合わせる、チームビルディングの手法の一つです。
まとめ
本書では、得た情報やプラクティスを自分たちの状況に照らし合わせ、それぞれの現場の背景や制約を考慮して捉え直すことの重要性を強調しています。
つまり「この本に記載されているプラクティスをそのまま応用するのではなく、自身の状況に合わせて工夫していかなくてはならない」というメッセージです。
社会に溢れている様々なノウハウ、ツール、情報を鵜呑みにするのではなく、自分なりに考え、改善を加えていくことが重要であると強く認識させられました。
本書は、ストーリーと解説を通して、具体的な生産性向上の取り組み(プラクティス)を紹介しています。一人から始められる取り組みと、社内外を巻き込んでいく取り組み、どちらも具体的で実践しやすいことばかりです。
巻末にはそれらが一覧でまとめられているため、いつでも参照できるように手元においておくと便利です。業務改善、生産性向上の実践に役立つ一冊です。