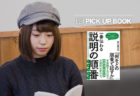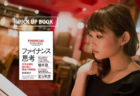新人のasatoと申します。毎回楽しみながら読書し、悩みながらも楽しく書評を書かせて頂いています。
今回ご紹介するのは『人生を変えるモノ選びのルール』です。著者の堀口英剛さんは、月間50〜70万PVの「気になるモノを幅広く紹介する」ブログ、「monograph」の編集長であり、株式会社dripの代表取締役でもあります。
堀口さんのことは本書が出版される前から存じており、ツイッターをフォローして、ブログも拝見していました。ブログを開くと、まずおしゃれなデザインに心を奪われます。また一つ一つの商品について丁寧にレビューされているので、興味を引かれて思わず買いたくなってしまいます。私はパンツハンガーを実際に購入しました。(本書内でも紹介されています)
さて、突然ですが、質問です。
- あなたは一張羅を持っていますか。
- 流行のデザインのモノを衝撃買いしたことはありますか。
- いいと思って買ったモノでも、家にある他のモノとうまく調和がとれていないと感じたことはありますか。
一つでも当てはまった方は、ぜひ読んでみてください。本書は、単純に堀口さんのオススメ商品を紹介する内容ではありません。タイトル通り、堀口さんが「モノと毎日の生活との関わり」について熱く語った一冊です。
本書の中で特に私の心に刺さったchapter1、chapter2、chapter3の内容をご紹介します。
①「ときめくモノ」をあつめよう
本書の中で「モノマリスト」という考え方が紹介されています。定義は
「モノ」を基軸に「生活」を考え、こだわりを持って愛情を注いでいる人
です。
私の場合、まず生活があり、生活に必要だから「あれが欲しい」となります。モノマリストと正反対です。この記事を読んでくださっている方の中にも、きっと私と同じ流れで買うモノを選んでいる方がいるのではないでしょうか。
堀口さんは、お気に入りのときめくモノのおかげで「毎日、毎朝、毎晩、ワクワクときめきを感じ」られていると言います。それらは「◯◯したい」という自分の願望を叶えるためのトリガー(きっかけ)になったり、集中するためのトリガーになったりするそうです。
自分に置き換えて考えてみると、このような力を持っているモノは思い当たりません。そこで、私の苦手なことの一つは料理なので、キッチンツールをいくつか新調してみました。いつもの鬱々とした気持ちで料理を始めても、新しいツールを使うと、確かに「あぁこれはあの時に買ったものだ」と思い出し、気分が上がってきます。今後はお気に入りの食器を探してみようと思います。
②「普段使い」にこそ一張羅を
冒頭で一張羅をお持ちかと質問しましたが、実は堀口さんは一張羅を持つことに否定的で、普段使いこそ「一張羅」を揃えるべきだという考えをお持ちです。一張羅とは「とっておきのモノ、特別なときに着る服」という意味なので、日常的に気を配るアイテムではなく、普段の自分にワクワクを与えてくれるものではないからです。
人生において「一世一代の大勝負」のような一生を左右する出来事というものは、いきなり起こるわけではありません。受験も就活も大事なプロジェクトのプレゼンも、すべては日々の積み重ねの結果。大事なのはその一日ではなくて、そこに至るまでの数十日、数百日です。
「普段使うものはすぐにダメになってしまう」という、正に本書に書かれている理由で、私はこれまでとにかく安いモノを選んでいました。これには小さい頃、母に大事なモノは使わずに取っておけばいいよ、と教えられましたことの影響があるかもしれません。しかし使わずにしまい込み、次に見つけたときにはもういらないモノになっていたという経験が数えられないくらいあり、本当にこれでいいのかと疑問を持っていたのです。
その疑問に対する、一つの答えを教えてもらった気がします。具体的な行動として、まずは早急に、値段で選んだ全くこだわりのないスマホケースを買い変えようと思います。
③「長く使えるモノ」を選ぼう
この章では、堀口さんのモノ選びに関する数々のルールが綴られており、どれも勉強になります。中でも私の心に響いたのは、「長く使えるか」という視点です。
一つのモノを自分の生活に迎えるか否かを考える際、私が一つの基準にしているのが「長く使っていけるか」ということ。
単純に、丈夫で耐用年数が長いモノを選ぶという話ではなくて、「長く使っていても飽きがこないか」「数年後も今と同じくらい、もしくはそれ以上に愛を持って使うことができるか」という視点でモノを選んでいます。
自分が使っているモノを思ったとき、私にもこのように長く愛用しているモノがあることに気づきました。
- 10年以上前に友人に誕生日プレゼントでもらい、毎日のように使っているレスポの化粧ポーチ。
- 5年以上前にバリに旅行に行った時、帰りの免税店で買ったグッチの定期入れ。
- 結婚したときに絵柄が気に入って自分で買ったマグカップ。
- 買ってからは必ず職場のデスクに置いて使っているペン立て。
これらは、年月が経った今でもどのように入手したのか、そのときのエピソードまで鮮明に覚えています。どんなに長く使っても、一度も買い換えようと思ったことがありません。普段そこまで意識していませんでしたが、これだけ長く使えるということは、私にとってのお気に入りの「ときめくモノ」たちなのだと思います。こうしたモノをたくさん増やしていきたいと思いました。
まとめ
本書の中では、モノに関する様々な表現がたくさん出てきます。
- 感情のトリガー
- 自分の背中を教えてくれる大切な「仲間」
- 優秀な「通訳」
- 自分を表現する手段
- 日々の生活を支えるパートナー
- 集中のためのトリガー
- 相棒のようなアイテム
- 長く寄り添える「パートナー」
これらの表現から堀口さんのモノへの愛情が感じられます。
本書を読んだ後、私は普段から他人の持ち物を観察するようになりました。また長く使い続けているモノに対する愛情が深まり、何かを買おうとするときは、一旦立ち止まって、それが欲しい理由や長く使えるかどうかについて考えるようになりました。
本書は自分とモノとの関わりを見つめ直し、新しい生き方を教えてくれる一冊です。